ベルギーのPMDリサイクル制度に学ぶ:市民意識とテクノロジーが支える循環型社会
今回も本コラムをお読み頂き誠にありがとうございます。日本シーム 岩渕でございます。
前回のコラムでは舞台をヨーロッパから日本に移しましたが、今回はまたヨーロッパへ戻り、ベルギーのPMDリサイクルについてお話ししたいと思います。ベルギーのPMDリサイクル制度は市民の高い協力意識と整ったインフラによって成立しており、その背景において日本と通ずるところがあるように思います。EU圏内でも最高水準のリサイクル率を誇るベルギーの事例から、日本の循環型社会形成に繋げるエッセンスを探ってみましょう。

ベルギーのリサイクルが誇る「PMD」とは?
まず、日本では聞き慣れない「PMD」という概念について説明したいと思います。PMDとは、Plastic bottles and flasks(プラスチック製ボトル・容器)、Metal packaging(メタル包装)、Drink cartons(飲料用紙パック)の頭文字をとった略語で、ベルギーの家庭ごみの中でリサイクル対象となる資源ごみの分類の一つです。日本における容器包装リサイクルの対象品に近いでしょうか。具体的には、以下のようなものがPMDに含まれます
•P(Plastic)
飲料や洗剤のペットボトル、シャンプー容器、ヨーグルト容器など
•M(Metal)
缶詰、アルミ缶、スプレー缶(中身が空であれば可)など
•D(Drink cartons)
牛乳パックやジュースの紙容器(アルミと紙が複合されたもの)
これらはすべて「軽量包装材」に該当し、一般ゴミとして焼却するのではなく、素材ごとに再資源化されることを目的に分別回収されています。ベルギーは今までのコラムで登場したドイツやスペインと比べて市民の分別意識が高く、その点において日本に近い背景を持っていると言えるでしょう。

「ブルーバッグ」から始まる分別と回収の仕組み
次に、PMDリサイクルの具体的な流れに触れてみましょう。ベルギーのPMDは、専用の青い袋(ブルーバッグ)に入れて家庭から排出されます。自治体によって収集日は異なりますが、通常は週に一度の定期回収が行われています。これらの袋は街中のスーパーマーケットや市役所などで手軽に入手可能です。お土産に・・・はならないかもしれません。
回収されたPMDは、ソーティングセンターに送られ素材ごとに分けられます。そして、素材ごとのベール品(圧縮梱包品)は需要に応じてリサイクラー等へリレーされていくというわけです。過去のコラムでもお話ししましたが、この巨大なソーティングセンターはヨーロッパにおけるリサイクルの大きな特徴の一つであり、ベルギーにおいてもやはりこのソーティングセンターが重要な役割を担っています。

選別精度98%の秘密 ― テクノロジーと手作業の融合
今回訪ねたブリュッセルのソーティングセンターでは、半径60km圏内の7つの自治体からPMDを受け入れ、1時間あたり22トンという膨大な量の選別を行っています。ヨーロッパの工場視察ではいつもその圧倒的な処理量に驚かされますが、驚くべきはその選別精度です。なんと、このブリュッセルの工場では出荷時点で98%の選別精度を誇り、まさに質と量の両立を成し遂げているのです。
現地担当者曰く、光学式選別機等を用いた自動選別で92〜94%、そして仕上げとしての手選別で98%という純度まで引き上げているということです。さらに、この98%という水準はベルギーのレギュレーション(法的基準)であるという衝撃の事実もお伝えしておきたいと思います。ドイツやスペインといったリサイクル大国に比べると絶対量が少ないため「ウチは質で勝負だ!」という経緯で高水準のレギュレーションが敷かれたそうです。天晴れ。

日本と通じる文化と制度の共通点
さて、冒頭でベルギーのリサイクルは日本に通ずるところがあると述べましたが、何を以てそう感じたか、少しお話ししたいと思います。第一に、市民の分別意識が高いという点が挙げられます。ベルギーのPMD制度がうまく機能している背景には、市民の高い環境意識と、それを支える教育や啓発活動の存在があります。学校では小学校からリサイクル教育が行われており、家庭でも親が子に分別の仕方を教える文化が根づいているといいます。また、誤った分別をした場合には袋が回収されず、その理由が明記されたステッカーが貼られるなど、家庭からの排出時点で比較的厳しい管理がなされているのです。
排出時点でのマテリアルの質という点でも、日本に近いと言ってよいと思います。そして第二に、PMD制度のスキームに相似点があります(先に補足をしておくと、これは「過去のベルギーが日本と似ていた」という事例です)。PMDの引受先は入札によって決まります。従来は日本の容リ同様単年契約を採用していたそうですが、近年に9年契約へ変更がなされたところ、一気に設備の大型化・集約化が進んでいったということです。リサイクルの質と量を拡大するためには、リサイクル産業における投資を活性化させればよいというシンプルな理屈だと思います。

「資源を活かす」社会づくりの鍵は、意識・制度・技術の連携にあり
気がつけば随分と長文になってしまいましたので、そろそろまとめに入ります。ベルギーのPMD制度は単なる分別ではなく、「資源を次に活かす」仕組みとして社会全体で共有されているように感じました。その鍵は、市民へのわかりやすいルール設定、回収の利便性、そして分別の徹底を支える教育とフィードバックの仕組みにあるようです。
また、他の環境先進国に比べると小国であるからこそ質にこだわっているという姿勢は、日本の目指すべきモデルケースの一つとして、数々のヒントがあると思います。ベルギーが体現しているように、循環型社会の形成には、市民の環境意識と制度、そして機械装置のテクノロジーが一体となることが不可欠であると改めて実感しました。あとチョコレートが美味しかったです。

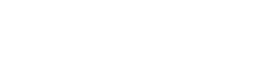
 洗浄粉砕機
洗浄粉砕機 破砕機
破砕機 高精度洗浄設備
高精度洗浄設備 粉砕機
粉砕機 切断機
切断機 水処理設備
水処理設備 微粉・細粒機
微粉・細粒機 乾燥機
乾燥機 プラ洗ユニット
プラ洗ユニット 洗浄脱水機
洗浄脱水機 減容・造粒機
減容・造粒機 選別機
選別機 混合機
混合機 分離機
分離機 搬送装置
搬送装置





























