日本と欧州のリサイクル政策を比較する:制度と思想の深層に迫る
今回も本コラムをお読み頂き誠にありがとうございます。日本シーム 岩渕でございます。
前回は初登場の国、ベルギーのPMDリサイクルについて筆を取りました。思い返せばヨーロッパ編のコラムも前回で3カ国目、記事にして9本目となりました。今年はもう一度訪欧予定がありますので、どんどん本数を伸ばしていきたいと思います。
さて、今回は欧州に関するコラムの記念すべき10回目、さらに私 岩渕がコラムを担当するようになってからちょうど1年ということで、改めて日本と欧州の比較コラムを認めたいと思います。以前に日本とドイツとの比較をしましたが、今回はより多角的で専門的な内容にしてみたいと思います。今回は大作です。どうぞお付き合いくださいませ。


日本と欧州、「制度」の違いよりも「思想」の違いが浮き彫りに
近年、日本国内におけるプラスチックリサイクル政策は、制度面では一定の整備が進んできたものの、欧州を中心とした国々と比べると、その設計思想や戦略的アプローチにおいて、決定的な違いが浮き彫りになってきています。とりわけ、リサイクルを「環境対策」ではなく「資源・経済政策」として位置づけ、循環経済(サーキュラーエコノミー)の中核要素として明確に捉える欧州の姿勢は、日本のリサイクル産業に携わる者にとって一考の価値があります。プラスチック資源循環促進法の施行や、容リ法の見直しが進む中で、日本独自の制度設計は現場の実情に即した工夫とも言えますが、一方で循環の質を問い直す国際的な視点とは、やや距離があるように思えるのです。
EUが2018年に発表した「欧州プラスチック戦略」は、単なるリサイクル率の向上にとどまらず、設計・製造段階から資源循環を前提とするサーキュラーエコノミー型のものづくりへと政策転換を進めてきました。ここでは、バージンプラスチックの使用削減が明確に数値目標として掲げられており、たとえばPETボトルには2030年までに再生材を30%以上使用することが義務化されています。
しかも、EUにおけるリサイクルの定義は物理的または化学的再資源化に限定されており、日本のように焼却によるエネルギー回収(いわゆる熱回収=サーマルリサイクル)をリサイクルとは見なしません。この点は、プラスチックの行方を循環の中に戻すのか、熱として消費するのかという、根本的な価値観の違いを示しているように思います。
こうした違いは、制度の文言の差異というよりも、政策が前提とする社会的・経済的基盤そのものの違いに根差しているのではないでしょうか。欧州ではリサイクル材の国内循環を強く意識し、一次資源からの脱却を産業政策の一部と位置づけているのに対し、日本は焼却インフラの充実を背景に、廃棄物管理の延長線上でリサイクルを位置づけている感があります。

焼却処理という“前提”がもたらす制度の柔軟性と課題
一方、日本のプラスチック資源循環促進法は、使用の抑制、再資源化の推進、設計段階からの環境配慮といった方向性を掲げてはいるものの、依然として熱回収をリサイクルの一形態として捉えていることから、欧州の定義とは根本的に立場を異にします。日本がこの立場をとっている背景には、高効率焼却炉が全国に整備されているというインフラ的側面や、都市部における廃棄物処理の現実があることも理解できます。
ただし、こうした制度的柔軟さは、循環経済という観点からみると、再生材市場の形成や製品設計段階でのリサイクル性向上の動機づけが弱くなるという副作用も伴っていると思います。焼却による熱回収が「手堅い処理手段」として広く認識されている限り、再生材の品質改善や用途開発への本格的な投資が後回しにされる構造が生まれかねない、とも言えるかもしれません。
一また、欧州における拡大生産者責任(EPR)の強化は、日本における同様の施策と比べてもはるかに重いものです。EUでは、製品のリサイクル性や再生材の利用率だけでなく、製品回収・処理の費用負担までもが法的義務として課されることが一般化してきています。この結果、企業はコスト削減と法令遵守の両立を図るため、リサイクルしやすい素材選定、単一素材化、分解しやすい設計への転換を加速させています。
これは、製品設計と資源循環を直結させるドライブシャフトであり、日本のリサイクル産業にも中長期的に影響を及ぼしていく可能性があります。近年では、国内でもEPRの見直し議論が徐々に高まりを見せており、産業界における対応準備が求められる局面に差し掛かっています。とりわけ、使用済製品のトレーサビリティ確保や、回収義務の履行方法など、制度実装面での課題は多く、環境機械メーカーとしても無関係ではいられません。

リサイクルから「循環の設計」へ。いま求められる視点とは
プラスチック資源循環をめぐる世界的な議論は、もはや「リサイクルするか否か」ではなく、「どのような設計思想で循環させるか」「いかにバージン材依存を脱却するか」という、より構造的なテーマへと移行しています。今後、国内制度も段階的に欧州型に近づく可能性は高く、我々現場サイドも、その流れを先取りして技術・製品を磨いていく必要があります。
制度の違いを知ることは、単なる比較ではなく、自社の戦略や技術開発の羅針盤として重要な意味を持つのではないでしょうか。特に、今後の日本においては、再生材の信頼性確保・流通ルートの整備・標準化の動きなど、制度面と市場面の両側からの双方向の整備が求められるはずです。循環型社会の中で環境機械が果たす役割は、単なる処理装置ではなく、資源化プロセスの司令塔としての価値を持つべき時代に入ってきているのかもしれません。

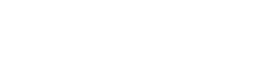
 洗浄粉砕機
洗浄粉砕機 破砕機
破砕機 高精度洗浄設備
高精度洗浄設備 粉砕機
粉砕機 切断機
切断機 水処理設備
水処理設備 微粉・細粒機
微粉・細粒機 乾燥機
乾燥機 プラ洗ユニット
プラ洗ユニット 洗浄脱水機
洗浄脱水機 減容・造粒機
減容・造粒機 選別機
選別機 混合機
混合機 分離機
分離機 搬送装置
搬送装置





























